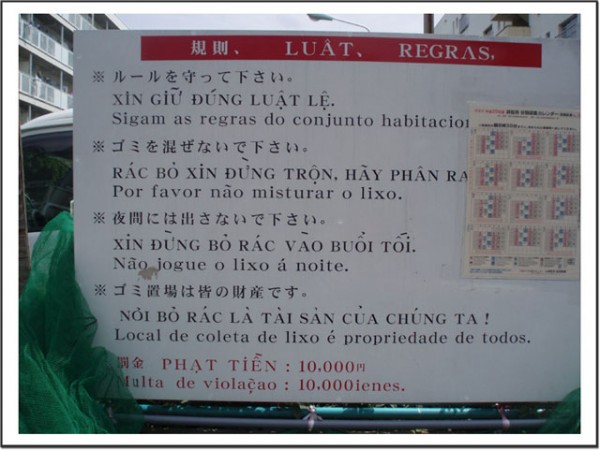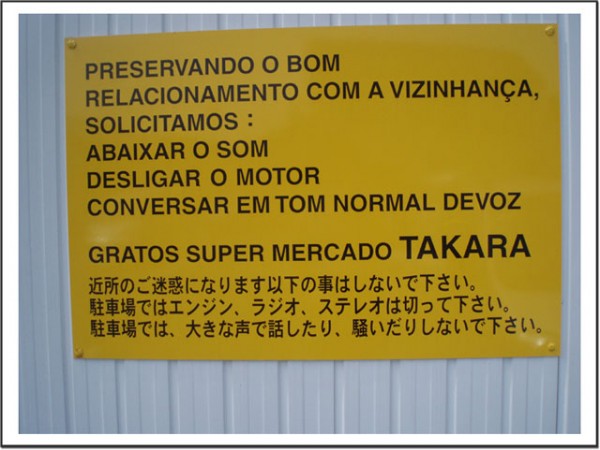【ギャラリー】原爆ドーム健全度調査中

原爆ドーム健全度調査中(2009年2月撮影、2009年11月掲載)
この写真は、原爆ドームを保存するために1992年から3年おきに行われている健全度調査の場面を写したものである。原爆ドームはこれまで1967年、1990年、2003年と3回の保存工事がおこなわれてきた。第二回の保存工事が終了するころ、原爆ドーム保存事業基金条例が制定された。建物の風化に対するこうした取り組みとして、今後は耐震補強工事を行うことが検討されている。
1996年、世界遺産に登録された原爆ドームは、修学旅行生や観光客が見物にくる場所である。これが位置する平和記念公園は広島市の中心部にある。そもそもこの場所は戦前には多くの人々が住む地域であったが、原子爆弾の投下によってほぼすべての人や建物が消失した。その跡地につくられたこの公園は、近くで働く人々が昼ご飯を食べたり休憩したりする場所にもなっている。
原爆ドームは、大正4年の建設当時としては珍しい、ヨーロッパ風の建築デザインである広島県物産陳列館(のちに広島県産業奨励館と名称変更)が前身である。これは広島市内にわずかに残る戦前につくられた建物であり、戦前と変わらず現在でも多くの人々がやってくる観光名所となっている。たしかに、原爆ドームは全国でも重要な観光地であるとともに、「保存」と「記憶」のための多大な努力と資金投入がなされている場所でもある。しかしながら、戦後直後はこれを保存せよという意見と、破壊してしまえという2つの両極端な意見があったことも事実である。原爆ドームを後世のために残していかなければいけない、という現在日本社会で主流となっている見方は、歴史的に生じたものなのである。
撮影:尾添侑太(博士課程後期課程)、文:濱田武士(博士課程前期課程)